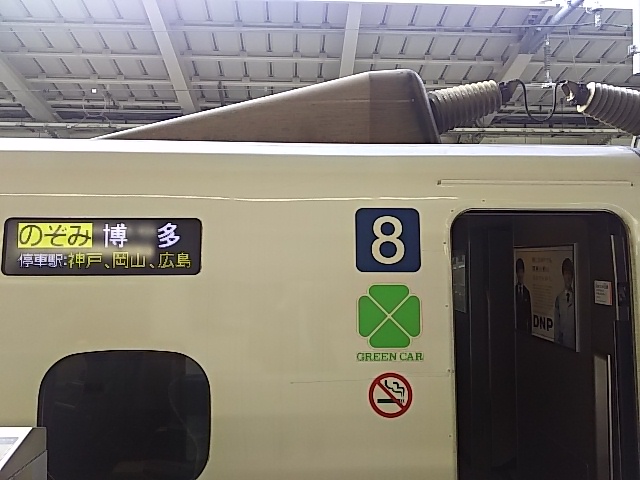名古屋-福井 北陸新幹線敦賀開業前と開業後の時間短縮を比較します
昨日の「大阪-福井 北陸新幹線で開通前よりも所要3分短縮のダイヤをみる」の名古屋-福井編です。
今回は、北陸新幹線敦賀開業前と開業後の、名古屋-福井のダイヤ状況を検証してみました。
大阪-福井の北陸新幹線3分短縮に対して、名古屋-福井も同じ3分の時間短縮でしょうか。
大阪編同様に、名古屋→福井と福井→名古屋の距離数相違により、上下列車を別々に検証します。
なお、名古屋発着の「しらさぎ」については、新幹線での名古屋-米原利用は考えず、名古屋-敦賀直通利用を前提とします。
米原止まりの「しらさぎ」については、新幹線での名古屋-米原利用を前提とします。
米原「しらさぎ」に接続する新幹線列車は名古屋時刻を()で示し、新幹線の名称と号数は記載を略させていただきます。
1 北陸新幹線開業前の名古屋・米原-福井「しらさぎ」の最速列車について
(1)名古屋・米原→福井 所要1時間38分
「こだま763号」名古屋7時37分発→「しらさぎ51号」米原9時15分着
※(次点)同9号・33号→1時間45分(日中の米原始発「しらさぎ」の4往復)
・最遅列車→名古屋~福井直通「しらさぎ」の所要2時間13分
(2)福井→米原・名古屋 所要1時間39分
「しらさぎ66号」福井20時55分発→「こだま766号」名古屋22時34分着
(次点)同52号、福井6時00分発、米原新幹線乗継、名古屋7時42分着→所要1時間42分
・最遅列車→福井~名古屋井直通「しらさぎ」の所要2時間13分
2 北陸新幹線開業後の「しらさぎ」「つるぎ」乗継時間の状況について
(1)名古屋・米原→敦賀→福井
・最速列車→「しらさぎ63号」~「つるぎ50号」の所要1時間34分
※名古屋→敦賀直通「しらさぎ」では「しらさぎ11号」の所要2時間10分
・最遅列車→「しらさぎ1号」~「つるぎ8号」の所要2時間15分
・全25往復の平均→2時間00分
・敦賀乗換平均時分→14分。8分間の乗換列車は1本、7%。乗換最長時分は19分
★列車別所要時間と、敦賀乗換時間の内訳で、号数は「しらさぎ」
名古屋発 米原発 敦賀着 敦賀発 福井着(敦賀乗換時間)
(7:04) 7:48 8:19 8:31 8:51「しらさぎ51号」(所要1:47※1時間47分、敦賀乗換12分)※以下同
7:51 8:57 9:27 9:46 10:06「1号」(2:15、19分)
8:51 9:56 10:27 10:43 11:04「3号」(2:13、16分)
9:48 10:56 11:26 11:39 11:59「5号」(2:11、13分)
(11:14) 11:56 12:26 12:42 13:02「53号」(1:48、16分)
11:48 12:56 13:27 13:41 14:01「7号」(2:13、14分)
(13:14) 13:56 14:27 14:41 15:02「55号」(1:48、14分)
13:48 14:56 15:26 15:41 16:01「11号」(2:13、15分)
(15:14) 15:56 16:27 16:39 17:00「57号」(1:46、12分)
15:48 16:56 17:26 17:38 17:58「11号」(2:10、12分)
(17:14) 17:56 18:26 18:39 18:59「59号」(1:45、13分)
17:48 18:56 19:27 19:39 19:59「13号」(2:11、12分)
(19:14) 19:56 20:26 20:43 21:03「61号」(1:49、17分)
19:48 20:56 21:26 21:42 22:02「15号」(2:14、16分)
(21:14) 21:50 22:20 22:28 22:48「63号」(1:34、8分)
(2)福井→敦賀→米原・名古屋
・最速列車→「つるぎ49号」~「しらさぎ64号」~「こだま768号」の所要1時間33分
※名古屋→敦賀直通では「つるぎ17号」~「しらさぎ6号」の所要2時間07分
・最遅列車→「つるぎ1号」~「しらさぎ2号」の所要2時間15分
・全25往復の平均→1時間57分
・敦賀乗換平均時分→9分。8分間の乗換列車は10本、67%。乗換最長時分は14分
★列車別所要時間と、敦賀乗換時間の内訳で、号数は「しらさぎ」
福井発 敦賀着 敦賀発 米原着 名古屋着(敦賀乗換時間)
6:36 6:57 7:11 7:45 8:51 「しらさぎ2号」(所要2:15
※2時間15分、敦賀乗換14分)※以下同
7:38 7:59 8:11 8:44 (9:25)「54号」(1:47、12分)
8:38 8:59 9:11 9:44 10:49 「4号」(2:11、12分)
9:41 10:02 10:10 10:44 (11:.25)「54号」(1:44、8分)
10:41 11:02 11:10 11:44 12:48 「6号」(2:07、8分)
11:41 12:02 12:10 12:44 (13:.25)「56号」(1:44、8分)
12:41 13:02 13:10 13:43 14:48 「8号」(2:07、8分)
13:41 14:02 14:10 14:44 (15:.25)「58号」(1:44、8分)
14:41 15:02 15:10 15:43 16:49 「10号」(2:08、8分)
15:40 16:01 16:09 16:43 17:49 「12号」(2:09、8分)
16:41 17:02 17:10 17 :43 (18:.25)「62号」(1:44、8分)
17:38 17:59 18:08 18:43 19:46 「14号」(2:08、9分)
18:41 19:02 19:10 19:43 (20:25)「64号」(1:44、8分)
19:42 20:03 20:15 20:49 21:54 「16号」(2:12、12分)
21:32 21:53 22:01 22:34 (23:05)「66号」(1:33、8分)
【結論】
名古屋→福井で(最大)4分短縮、福井→名古屋で(最大)6分短縮だった
15往復全体の平均を見ると、名古屋→福井は所要2時間00分、福井→名古屋も2時間00分で、同時間でした。
名古屋・米原→福井直通時代の最速列車1時間38分と比べ、新幹線開通後は最速1時間34分で、4分の短縮です。
福井→米原・名古屋は直通時代は最速1時間39分、新幹線開通後1時間33分で6分短縮です。
最も遅い列車で比較すると、直通時代は両方向とも2時間13分、新幹線開通後2時間15分で新幹線効果はありません。
敦賀での新幹線接続が、在来線から新幹線の場合は大阪側「サンダーバード」優先、新幹線から在来線は米原「しらさぎ」優先ダイヤです。
福井→米原の場合、敦賀8分乗り継ぎが15列車のうち10列車、67%あることで速達乗り継ぎダイヤにはなっています。
米原→福井では敦賀8分乗り継ぎは1本だけで、あとは12分以上かかり、最長19分接続です。
敦賀での新幹線接続がなかったときは、「しらさぎ」と「サンダーバード」の運転間間隔は最小限でも5分は空けていました。
新幹線敦賀での同じ「つるぎ」接続で、2列車を4分に縮めた結果ですが、近江塩津-敦賀での特急続行運転には4分空けることが限度とみられます。
「つるぎ」は毎時2往復が基本ダイヤであるならば、「しらさぎ」と「サンダーバード」とを同じ「つるぎ」に接続しなくてもよいのではないかとも思います。
「つるぎ」でも速達型と各駅停車型があり、金沢行きと富山行きの2種が絡み合い、さらに一部は臨時列車扱いです。
また、東京行き「かがやき」「はくたか」の接続を避けたダイヤでもあり、これらが相互に、複雑に絡み合います。
名古屋-福井に特定して見てみると、敦賀-福井で越前たけふを通過すると17分、停車すると21分で4分差です。
新幹線開通前の「サンダーバード」は京都-金沢で福井のみ停車のタイプもありましたが、「しらさぎ」は北陸新幹線の各駅に停車するタイプのみでした。
その意味では「しらさぎ」の一部は各駅停車型「つるぎ」に接続という考えもあるかと思います。
敦賀で19分待ちならば、各停「つるぎ」8分乗り継ぎにより全体時間を相殺するという考え方もあります。
それによって、「しらさぎ」「サンダーバード」の両列車の敦賀8分乗り継ぎを果たすのも一方法かと考えますが、いかがでしょうか。

※写真は本文と無関係です。